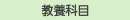2025年度福島学 第1回フィールドワーク
~双葉町・大熊町・浪江町エリア~
被災地の現地フィールドワークがプログラムされているのが福島学の特徴の一つです。第1回フィールドワークでは双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館、大熊町の中間貯蔵事情情報センタ―・中間貯蔵施設、浪江町の震災遺構 浪江町立請戸小学校を見学しました。「3.11の教訓を自分事として考える!」といった学生の学ぶ姿勢が伝わってきました。


中間貯蔵施設の見学の模様です。視線の先には東京電力福島第一原子力発電所が見えました。
第一原子力発電所から直線距離で1.2キロです。

原子力災害伝承館にて、語り部の方から説明をいただきました。

除去土壌が保管されている場所で線量計にて放射線量のチェック。
「放射線とか大丈夫だったの?」と母に言われた。「除染された土がどれだけ安全に処理されたか」ちゃんと説明も聞いたし、実際に線量計で測ってきたよ」と、ドヤ顔で母に説明できました。

到達した津波の高さを見上げてみる。小学校を飲み込む津波はどれだけ怖かっただろう。

伝承館のイントロは、福島の美しい自然や歴史を伝える小さな画面から。

帰還できないエリアの看板@双葉町

津波に飲み込まれた水産資源研究所。3.11の津波の威力がそのまま見て取れる・・・@大熊町
【学生の感想より】
*中間貯蔵施設を見学して、普段はなかなか近くで見られない原子力発電所や震災当時のまま残っている建物や高齢者施設「サンライフおおくま」等を間近で見て、当時の私は、まだ小さくて震災のことはあまり覚えていないが、今回見学するにあたって、改めて震災当時の被害の大きさを感じ、知ることができた。また、それと同時に少しずつ住んでいた人々が戻って来ていて、復興に近づいているということも、感じることができた。特に、放射線量の測定器で線量を測った時に、除染土壌よりも林の方が実際には多くの線量があることを知り、実際に体験してもっと多くの人に伝わってほしいし、伝えていきたいと改めて思った。
*正直、福島学を受講する前は、ニュースで目にするだけで、復興に向けての取り組みをよく知らなかった。放射線量が下がっているといっても不安があったが、自分の目で確かめることで納得することができた。不安や疑問があるのは、知らないからなのだと気づくことができた。また、安全対策が万全にされている様子を見たり、再生利用の実証実験を見て、周りへの理解を広めていきたいと思った。
*専門家の調査で原子力発電所の場所に1000年前には10m越えの津波がきていたということが分かったにもかかわらずすぐに対処していなかった。
*実際に現場へ赴くことで当事者意識をもち福島の未来について考える機会が増える。

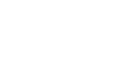 受験生の
受験生の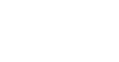 在学生の
在学生の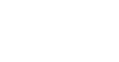 資料請求
資料請求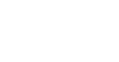 オープン
オープン