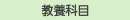第6回福島学「浪江・双葉・富岡状況とホープツーリズムの理解」
本日のゲストティーチャーは、(公財)福島県観光物産交流協会 ホープツーリズムサポートセンターより高橋 良司様をお迎えしました。
世界で類を見ない 「複合災害(地震・津波・原子力災害)」 を経験した唯一の場所、福島県。ホープツーリズムとは、複合災害の事実、教訓、復興への挑戦から得た学びから、これからの持続可能な社会・地域づくりを探究・創造する福島県独自のプログラムのことです。
つまり、福島県でしか得られない新しい学びのスタイルということなんです。
ホープツーリズムは、福島県をフィールドとして見る・聞く・考えるを盛り込んだオンリーワンの学びを実現しています。
見るとは?震災伝承館や福島第一原子力発電所の見学を通じて震災と復興についてフィールドワークを通じて学びます。
聞く?とは様々な立場・分野で復興に“挑戦”する人々との“対話を通じて多くの気づきを得ることができます。
考えるとは?震災・原子力災害の教訓を未来(社会・地域・日常・自分自身)にどう活かすかを考え続けることに繋がります。
こう考えると、ホープツーリズムは桜の聖母短期大学で開講している「福島学」と通じ合う学びとも言えます。
今回受講した学生は、高橋様よりまた新たな視点気づきを得たようです。
学生の印象に残った言葉
・ホープツーリズム
・ふるさととは
・考える力
・フィールドパートナー
・「もやもや」を持ち帰る
・考える力
学生の感想
・考える力というのは、本当は簡単に答えが出ない問いを考え続けることなのではないかということを聴いて、本当の意味では簡単に答えを出すために考えることは考える力とは言わない。
・フィールドパートナーをつけることで沢山の論理的見方を聞いたときに参加者の考察力、創造力を引き出すことができる所に素晴らしさを感じた。
・母校であるふたば未来学園でホープツーリズムを経験しており広野町でフィールドワーク、取材をして演劇にした。福島の教訓、現在の問題を正しく知るには現地に住む方に直接聞くことが一番の近道と考察する。このように学校教育からホープツーリズムをすることで若いうちに相双地区への関心が深まり未来を担う若者となる。そうすることで持続可能な社会に繋がると理解した。
・誰にも正解が分からず不安に思ってしまうかもしれないが、正解がないからこそ最後まで向き合う必要があると考える。
・実際に富岡町の事例を聞いて、移住者に対して補助金を支給したり、子育て世代に対しても経済的援助を行ったりと人口を増やす対策をしている一方で、まだまだ交通の便や商業施設などが不十分であるといった課題が多くあることに気づいた。

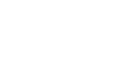 受験生の
受験生の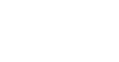 在学生の
在学生の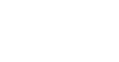 資料請求
資料請求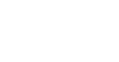 オープン
オープン